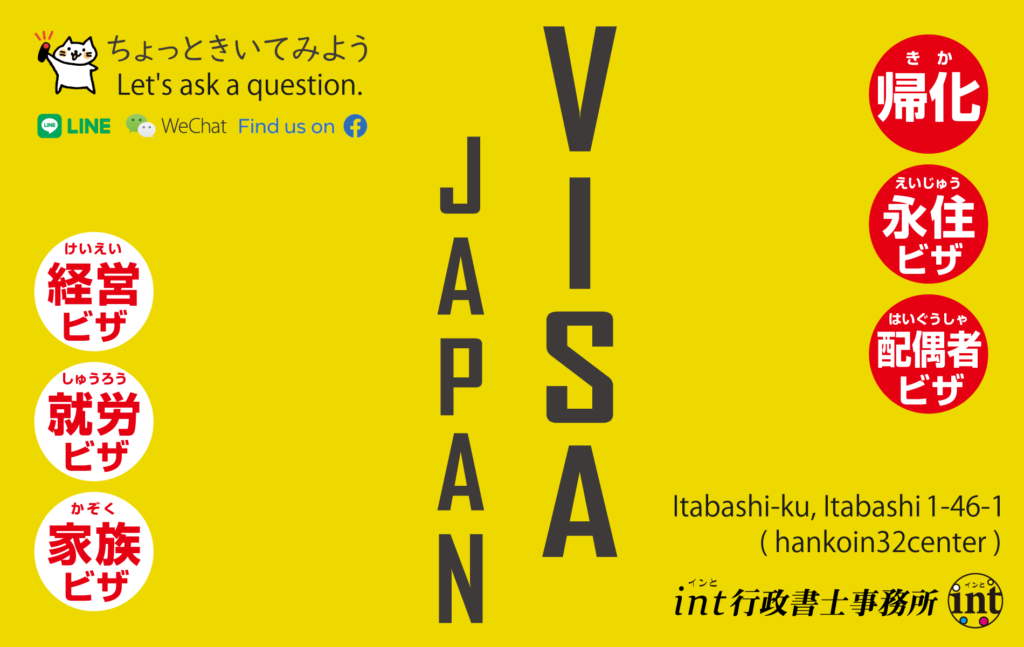帰化の概要
日本には現在いろいろな国の人々が住んでいます。
令和2年の6月時点での在留外国人の数は、およそ288万人にもおよびます。
中国、韓国、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ネパール、インドネシア、台湾、米国、タイのかたなど、その国籍はさまざまです。
(以上は、令和2年現在の在留外国人の国籍別トップ10です。)
こういった方々が、日本の国籍を取得したい、つまり日本に帰化したいと思ったときに行う手続きが、帰化許可申請です。
帰化とは、一般的には、ある国の国籍を有しない特定の者からの同国の国籍の所得を希望する意思表示に対して、同国の国家機関が許可を与えることによって同国の国籍を取得することを言います。
日本では、日本国民でない者が本人の志望に基づいて申請(帰化許可申請)をし、法務大臣の許可により日本の国籍を取得することができる仕組みとなっています。(国籍法第4条)
帰化の申請は帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由してすることを要します(国籍法施行規則2条1項)。この申請は、申請をしようとする者が自ら管轄の法務局又は地方法務局に出頭して、書面によってしなければなりません(国籍法施行規則2条2項)。
法務大臣は、国籍法が定める要件を備えているかどうかを審査し、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならないとされています(国籍法10条1項)。
帰化は告示の日から効力を生じます(国籍法10条2項)。
また、官報告示の日から1か月以内に、市区町村長に戸籍法上の帰化届をしなければなりません(戸籍法102条の2)。
帰化の要件
まずは帰化の基本的な6つの要件を確認して、自分がこの要件に当てはまっているかを確認する必要があります。
1,引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
まず、帰化申請をするときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していなくてはなりません。
この条件が必要とされるのは、帰化が認められると日本国民となるのですから、日本に一定期間生活の本拠を有し、日本社会に馴染み、日本社会に同化していることが必要だからです。
また、5年間の居住期間に中断がある場合には、原則としてこの要件は満たさないこととなりますので注意してください。
ただし、以下のような場合には、1の要件は免除となっています。
①日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
②日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条2号)
③引き続き十年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)(国籍法6条3号)
④日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
⑤日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)
⑥日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
⑦日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの(国籍法8条2号)
⑧日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
⑨日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
なお、帰化要件が緩和される場合(簡易帰化)の詳細については以下の記事に詳細をまとめてありますので御覧ください。
2,18才以上で本国法においても成人であること(国籍法5条1項2号)
帰化許可申請者は18才以上(2022年4月の民法改正のより成人年齢引き下げに伴い変更)であり、かつ本国法(申請者の国の法律)においても成人していることが条件となります。
ただし、上記の要件1で記載した④~⑨に該当する場合には、当条件も免除となります。
未成年者の場合、一人で帰化申請をしても当条件が満たされませんが、親が帰化申請をすれば、親の帰化が許可された時点で上記⑥に当てはまるため、実際は親と未成年の子は一緒に申請をして親子同時に許可が認められることとなります。
3,素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことをいい、ひとつの見解として、刑事罰、行政罰、租税の滞納処分、地域社会への迷惑の有無等を勘案してその判断がなされます。
これは、日本の社会の安全と秩序を維持するためです。
よく引っかかってしまう項目としては交通違反です。勤務上の理由などで車の運転が多い方は特に気をつけたほうが良いでしょう。
また、経営者であれば納税や労働法令違反等にも注意が必要です。
4,自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)
生計を一にするとは、世帯よりも広い概念であり、同居を必須とはしていません。例えば親から仕送りを受けて生活している学生などもその対象となります。
また、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母など、自力では生計を営むことができないものであっても、生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に判断して、生計を営むことができれば良いこととされています。
この条件は、現在および将来にわたって公共の負担になることがなく、安定した生活を営むことが出来るか否かをみるためのものです。
5,国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
帰化申請者は、無国籍か、又は日本の国籍を取得することによってそれまで有していた国籍を失うものでなければなりません。
なお、例外として本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。(国籍法第5条第2項)
6,日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)
帰化申請者は、憲法や政府を暴力で破壊するといった行為や主張をするものであってはなりません。またそのような団体を結成したり、これに加入したことのない者でなければなりません。
なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
また,日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
下記の記事は、普通帰化の要件をやさしい日本語で説明したものです。よろしければこちらも合わせてご覧くださいませ。
関係法令等
リンク先:e-gov法令検索
参考リンク
帰化許可申請(リンク先:法務省)
国籍(リンク先:東京法務局)
参考書籍・参考文献
帰化・永住・在留許可申請業務(リンク先:Amazon)
国籍の得喪と戸籍実務の手引き(リンク先:Amazon)
帰化の要件が緩和されるケース(簡易帰化)

簡易帰化(要件緩和)の9つのケース簡易帰化とは?帰化の要件には、こちらのページでご説明...
続きを読む帰化申請手続きの流れ

帰化申請の流れ帰化申請は、本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書...
続きを読む帰化申請の作成書類

帰化申請の書類帰化申請に必要となる書類は、個々の状況によって異なりますが概ね以下のとおりです。...
続きを読む帰化申請の取り寄せ書類

帰化申請の書類帰化申請に必要となる書類は、個々の状況によって異なりますが概ね以下のとおりです。...
続きを読むレッツ ゴー ふ あん は フフフ の フ050-710-77707※留守番電話になりましたら、メッセージをお願い致します。当方より折り返しご連絡致します。(Tel No,末尾5554より)
お問い合わせはこちら どうぞお気軽にご連絡くださいませ。